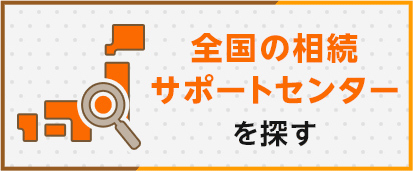はじめての相続について
FIRST
遺言の執行実務
“トラブル”を防ぐ遺言の遺し方とは?
折角遺言書が残っているのに、その表現方法が曖昧だったり、配慮に欠ける書き方をしてあるばっかりに、かえって遺言執行にあたってトラブルに発展するケースがあります。
ここでは、そうしたトラブルの実例を挙げながら、トラブルを防止する遺言の遺し方を示していきます。遺言書作成の参考にしてください。
遺言の執行実務の流れ
遺言執行者は遺言によって指定される場合と、家庭裁判所から選任される場合があります。
特定の者に指定したいのであれば、遺言の中で執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をすることができ、相続人もこれを妨げることは出来ません。
Step:1 就任報告
遺言執行者は、遺言者が亡くなられたという通知を受けると同時に、相続人に対し、遺言執行者に就くことを連絡。
Step:2 財産目録作成
財産目録を作成し、相続人へ報告。
Step:3 遺言執行
遺言の内容に従って遺産を処分。名義変更や財産の引渡しなど、相続人へ遺産を分配。
Step:4 完了報告
相続人へ遺言執行の完了を報告。
現場でよく起きる遺言の問題点とその対策
あなたのその遺言が、トラブルの種になるかもしれませんよ?
折角遺言書が残っているのに、その表現方法が曖昧だったり配慮に欠ける書き方をしてあるばっかりに、かえって遺言執行にあたってトラブルに発展するケースがあります。
ここでは、そうしたトラブルの実例を挙げながら、トラブルの防止策を示していきます。
事例1
相続人がなかなか確定できずに、所有権移転登記がスムーズに出来なかった。
上記トラブルの防止策
できる限り、遺言書作成時点で相続人の確認作業を行っておきましょう!
事例2
遺留分減殺請求を受けたために、スムーズに遺言執行が出来なかった。
上記トラブルの防止策
- 遺留分のことを十分に理解した上で遺言書を作成する
- 減殺請求されたときの対応策を遺言書の中に明記しておく
- 遺言書作成時の遺言者の考え方を明確に相続人全員に伝えておく
- (または、遺言者の死後に執行者が正確に伝える)
事例3
遺言書を書き直したために取り分が減った相続人がいて、なかなか納得してくれなかった。
上記トラブルの防止策
既存の遺言書の一部もしくは全部の内容を取消す場合は、新たな遺言書に全てを記載し直すこととし、変更前の遺言書は極力処分しておくことをお勧めします。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
えひめ三福相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
えひめ三福相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載